花言葉は、私たちの生活に深く根ざしています。特別な日には花束を贈り、その花言葉を通じて感謝や愛情を伝えます。
しかし、これらの花言葉は一体誰が、どのようにして決めたのでしょうか?
この記事では、花言葉を決めたのは誰なのか、その決定プロセス、地域や時代による違い、そして日本での花言葉の歴史と現代への影響、さらには誤解と誤用についてまで、花言葉の全てを詳しく探っていきます。
Contents
花言葉は誰が決めた??
花言葉を誰が決めたのか?これに対する答えは・・・分からない!というのが答え。
花言葉は、とくに誰が決めたということが分かっていないのです。
花の持っている特性やイメージなどから、少しずつ時代ごとの社会的背景などの影響も受けながら少しずつ形作られていったものです。
もちろん、爆発的に花言葉が作られ広まった時代が大きく影響しているのは間違いないでしょう。
どうやって花言葉が現在のような形になっていったのか詳しくみていきましょう。
花言葉の由来と起源
まずは、花言葉がどうやって始まったのかという由来について紹介します。

花言葉の起源・由来
花言葉の起源は、古代ギリシャやローマ、中国など、古代の文化にまで遡る(さかのぼる)ことができます。
これらの文化では、花は神々への奉納や祭りの装飾として使われており、花に意味をもたせて神々へのメッセージを伝えるのに利用されていたのです。
神々へのメッセージとして利用されていましたが、いつしかヒトに対しても愛を表現したりするために使われるようになったのが『花言葉の由来』と言われています。
そして、現代の花言葉のシステムは、19世紀のヴィクトリア時代のイギリスで発展しました。
花言葉はヴィクトリア時代の貴族の間で人気だった
花言葉の起源は明確ではありませんが、19世紀ヴィクトリア時代のイギリスで広まったとされています。
この時代に草や花を人に見立てた手書きの『まとめ集』が人気だったのです。これを貴族仲間で回し読んでいたとされています。
この中身は特に草花の特徴から、
- この花は〇〇の特徴があるので美しさを際立たせている!
- この花は△△だから、不実さを表している!
といった感じで、今の花言葉のようなものを思い思いに書き記していたのです。
この『まとめ集』を読んで、恋人の美しさを褒めたり、浮気を非難したりと恋愛の手引きのように使われていたようです。
花言葉をさらに広めたのは
貴族間で人気だった『まとめ集』。これをきちんとまとめたのがヴィクトリア時代のイギリスで活動した『シャーロット・デ・ラ・トゥール』という人物。
シャーロットは1834年に「花の言葉」という本を出版し、初めての花言葉辞典として流行がさらに広がりをみせたのです。
なぜ花言葉はそこまで人気だったのか
ヴィクトリア時代の厳格な社会規範が人気の理由です。
当時の社会では直接的な感情表現が制限されていたため、花を通じて間接的に感情を伝える方法が求められたのです。
この習慣は花の贈り物や花の装飾が一般的だった社会的な背景により、急速に広まったのです。
花言葉はどのようにして作られたのか?
花言葉は、その花の特性や見た目、花が咲く季節、花の色など、さまざまな要素に基づいて決定されます。
また、花の名前の響きや、その花にまつわる伝説や物語も、花言葉の決定に影響を与えます。

花言葉の決め方
花言葉の決め方は、その花が持つ特性や、人々がその花に抱く感情、またはその花が伝えるメッセージに基づいています。
- 花が育つ環境
- 花の咲き方(長い期間咲くなど)
- 色のイメージ(たとえば赤色は情熱的だ!など)
- 花の見た目(1輪だけ咲くなど)
- 花を使った昔話や神話など
- そのほか、花の特徴から
例えば、
- 赤いバラには「愛」という花言葉がありますが、これは赤色が情熱や愛情を象徴する色とされているため。
- タンポポは生命力が強く生きる特性から、「希望」という花言葉をもっている。
- ひまわりは太陽に向かって咲くという性質から、「崇拝」「あなただけを見つめます」という花言葉。
- 桃は「天下無敵」という花言葉があり、これはイザナミノミコトが桃を投げつけて鬼を追い払ったという言い伝えから。
花言葉は1つの花にたくさんある
花言葉は、1つの花に1つだけではありません。これは花に対する考え方が、地域や時代によって異なることがあるためです。
例えば、西洋では赤いバラは「情熱的な愛」を象徴しますが、東洋では「義務や責任」を象徴することもあります。
これは、文化や歴史、宗教などが花言葉に影響を与えるためです。
花言葉は国によって違う?
日本と海外では同じ花でも国や地域によって意味が異なることが多くあります。

東洋と西洋の花言葉は違う
東洋と西洋の花言葉には、共通点と違いがあります。
例えば、西洋ではバラは「愛」を象徴しますが、東洋では「美」を象徴することが多いです。
さらに色や種類によって意味が細分化されています。また、一部の花は、東洋と西洋で全く異なる意味を持つこともあります。
例えば
- ひまわり・・・日本「崇拝」、海外「幸運」
- ガーベラ・・・日本「希望」、海外「上機嫌」
- ラベンダー・・・日本「沈黙」、海外「献身的な愛」
などなど。ほんの一例ですが、日本と海外で全然違う花言葉ということは珍しくありません。
花言葉はなぜ国よって違うの?
花言葉は、その地域の文化や風土、宗教に大きく影響しているからです。
たとえば「黄色」は海外だとあまり良いイメージカラーではない国があるといった感じです。
また同じ種類の花でも、咲く場所が違えば、その花に対するイメージが違うためです。国が違えば言葉自体も変わるように花言葉の意味も変わってくるのです。
花言葉はいつから日本で使われているの?
花言葉は、明治時代に西洋から伝わったとされています。
それ以前の日本にも、花に対する独自の感情表現は存在しましたが、現在のような「花言葉」の形は西洋からの影響が大きいため開国した明治時代から使われるようになりました。

花言葉の日本における歴史
花言葉の歴史は、日本の歴史と深く結びついています。
古代から中世にかけて、花は神々への奉納や祭りの装飾など、さまざまな目的で使用されてきました。和歌や俳句などの詩文にも花が頻繁に登場し、その花が象徴する感情や季節感を表現する手段として用いられてきたのです。
しかし、花に意味がもたされていたものはありますが、ほんの一部の草花だけでした。
多くの花言葉が日本に伝わったのは、明治時代の西洋文化の流入とともにです。
その後、日本独自の花言葉も生まれ、例えば桜の「儚さ」や菊の「高貴」など、日本の文化や感性が反映された花言葉が多く作られたのです。
まとめ
この記事では、花言葉の起源と歴史、決定プロセス、地域や時代による違い、そして現代への影響について詳しく解説しました。
記事の中で伝えたい大切なポイントをまとめます。
- 花言葉を誰が作ったのかは、分からない。
- 花言葉の起源は、古代神々へのメッセージ。
- 花言葉は、19世紀のイギリスで爆発的に広まった。
- 花言葉は、花の持つ性質、イメージ、季節、色などから作られている。
- 花言葉は日本と海外で全然違うことがあるが、これは風土、文化、宗教によって影響されているため。
- 花言葉が日本に伝わって現在の形になったのは、明治時代から。
花言葉の由来、どうやって作られているのか分かったでしょうか。私たちの生活や文化に深く結びついていて影響を与えられていましたね。



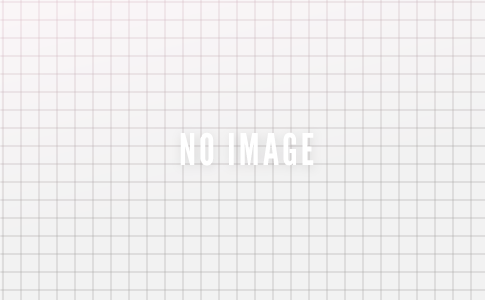





コメントを残す